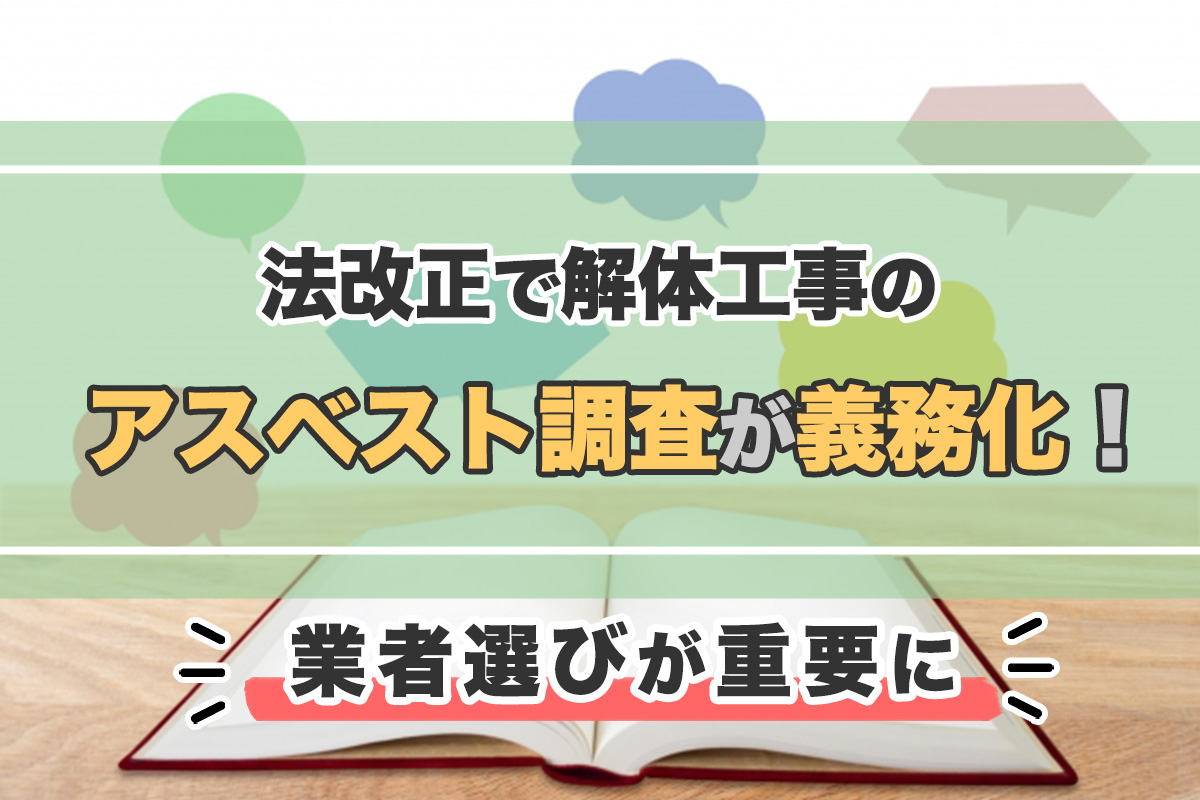
法改正により、解体工事を行う前にアスベスト調査が義務化されたことをご存知でしょうか。
解体工事に伴うアスベスト(石綿)飛散防止対策の一層の強化を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年(2020年)6月に公布されました。
一部の規定を除き、令和3年(2021年)4月から施行されています。この改正によって解体工事の前にアスベスト調査が義務化され、アスベスト調査を行わなければ解体工事の補助金を申請することもできません。
しかしこれらのことは、解体業者もまだ十分に把握していない可能性があります。
そこで本記事では、法改正によって解体工事におけるアスベスト対策はどう変わるのか、そしてアスベスト調査や除去工事の流れ、補助金制度などについて詳しく紹介します。
目次

今回の法改正に伴い、解体工事やリフォーム工事を行う前には、工事規模の大小に関わらず設計図書や目視によるアスベスト調査が義務化されました。
これにより業者側は、解体工事着工前に「目視」により建材が設計図書などと整合していることをチェックする必要があります。
また、使用されている建材を特定してメーカーに成分情報等を確認することで、アスベスト使用の有無をチェックしなければなりません。
設計図書がない場合は目視確認のみで良いことになっていますが、壁の内部などの目視確認が困難な箇所であっても、目視が可能となった際には調査を行わなければなりません。
そして調査結果を解体工事現場に掲示すると共に、3年間の記録保存が義務付けられます。
一方、平成18年(2006年)9月以降に着工された住宅や製造された建材に関してはすでにアスベストの使用が禁止されています。
そのため、当該着工日や製造日等の確認を行うことで事前調査とすることができます。
アスベストとは「石綿(せきめん、いしわた)」と呼ばれる天然の鉱石のことをいいます。
熱に強く安価なため、建物の火災防止目的で2005年頃までさまざまな箇所に使用されてきました。
代表的なものとしては、鉄骨造建築物などの耐火被覆材や住宅用屋根化粧スレート(カラーベスト)、アスベスト含有断熱材、ロックウール吸音天井板などがあります。
ところが、アスベストを吸い込むと肺がんや悪性中皮腫などの原因となるリスクが高いことが分かり、徐々に使用が禁止されるようになりました。
また、平成18年(2006年)9月には0.1重量%を超えるアスベスト含有製品の製造、使用が禁止されるようになりました。
しかし2006年以前に建築された建物の一部では、アスベスト含有建材が使用されている可能性があります。

ここでは、解体工事前のアスベスト調査のおおまかな流れは以下になります。
以下ではそれぞれの流れを詳しく紹介します。
アスベストの事前調査は、アスベストに関する一定の知見を有し、的確な判断が出来る者が行うこととなっています。
例えば、建築物アスベスト含有建材調査者や一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者などが事前調査を行うことができます。
また、令和5年(2023年)10月1日からは建築物のアスベスト調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務付けられます。
義務付け適用開始前であっても、可能な限り必要な知識を有する者に調査を依頼しておくと安心です。
このように、アスベスト調査には法改正に対応している業者選びが重要になります。
悩んだら地方自治体もしくは専門家(調査会社、建築設計事務所、工務店など)に相談してみると良いでしょう。解体エージェントでご紹介することも可能です。

アスベスト調査では設計図書等による書面調査と目視による現地調査は必須事項で、必要に応じて現場で採取したサンプルをもとに分析調査を行います。
この際、設計図書などの書面のみで「アスベスト使用なし」と判断せずに、必ず現地で各部屋・部位の確認を行うことが重要です。
また、解体工事の施主(発注者)は自分自身だけでなく工事関係者や周辺住民に対しても健康被害を及ぼす可能性があることを意識する必要があります。
そのため、アスベスト調査に協力することや、設計図書等の提供や調査費用を負担する義務があります。
アスベスト調査不徹底により法に定められた届け出対象工事が未届けの場合は、届出義務者である施主(発注者)が法の罰則対象となることもあります。
前述したように、令和4年(2022年)4月1日以降はアスベスト含有建材の有無にかかわらず、元請業者等がアスベスト調査結果を都道府県等へ報告することが義務付けられます。
また、令和3年4月以降は施主への説明とアスベスト調査の結果を記録を作成して3年間保存することが義務付けられています。
令和3年(2021年)4月以降は、解体工事を行う前に工事に関わる全ての材料について実施したアスベスト調査結果を、工事現場の見やすい箇所に掲示する必要があります。
調査の結果アスベストが含まれない場合であっても、必ず掲示が必要です。

この章では、解体工事におけるアスベスト除去工事の届け出と流れについてを紹介します。
アスベスト除去工事に関連する法律と届け出には以下のようなものがあります。
吹付けアスベスト、アスベスト含有耐火被覆材、アスベスト含有保温材等特定建築材料の除去工事を行う際には注意が必要です。
工事の施主(発注者)が工事開始の14日前までに都道府県知事に届け出る必要があります。
耐火・準耐火建築物の吹付けアスベストの除去作業を行う際には、工事開始の14日前までに施工業者が労働基準監督署長あてに届け出を行います。
建築物アスベスト含有保温材、アスベスト含有耐火被覆材、アスベスト含有断熱材の除去などを行う場合、施工業者が工事開始前までに労働基準監督署長あてに届出を行います。
アスベストに強い解体業者を見つける
アスベスト除去工事の大まかな流れは以下の通りです。
なお、一般的な流れになるので、建物の状況や周辺状況によって多少異なる場合があります。
| 近隣へのご挨拶 |
| ↓ |
| 引き込み配管、引き込み配線の撤去 |
| ↓ |
| 足場の組み立て、飛散防止用シート掛け |
| ↓ |
| 建物内部の残置物、畳、襖、障子、住宅設備機器等の撤去 |
| ↓ |
| アスベスト除去 |
| ↓ |
| 建物内部(その他の内装材、サッシ等)の解体 |
| ↓ |
| 建物本体の解体(小屋組、柱・梁等の構造躯体、基礎等) |
| ↓ |
| 廃材の分別、収集、搬出 |
| ↓ |
| 地中障害物の有無の確認、整地 |
アスベスト除去工事では、室内の天井材、壁材及び屋根材、外壁材などのアスベスト含有建材の撤去を行います。
除去したアスベスト含有建材は丈夫な袋や容器に密閉して保管し、内容物がアスベスト廃棄物であることを明示します。
また、除去したアスベストの運搬や処分は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して適切に処分することが大切です。
アスベスト除去工事の流れ、近隣挨拶のマナーについては、以下の記事を参考にしてください。

アスベスト飛散防止対策については、今回ご紹介した大気汚染防止法以外にも、さまざまな法律による制限や規制があります。
平成18年(2006年)10月1日以降に着工する建築物については建築基準法により、アスベストの飛散の恐れがある建築材料の使用が禁止されました。
増改築時には原則として既存部分のアスベスト等規制材料の除去が義務付けられ、アスベストの飛散の恐れがある場合は、除去等の勧告・命令ができることが定められています。
「廃アスベスト等」または「アスベスト含有産業廃棄物」については、適正かつ確実な処理基準等が定められています。
解体工事等に際し、事前措置を適正に行うために定められた法律です。
特に分別解体等を行う際には、アスベスト関係法令に従い各種届出を行って、他の建築廃棄物の再資源化を妨げないように適正に施工・処理することが求められています。
労働者の健康を守るために定められた法律です。
建築物の解体時におけるアスベストの除去作業届出や事前調査、作業計画や特別教育、作業主任者の選任、保護具着用、作業場所の隔離、立入禁止等の規定が定められています。

民間建築物のアスベスト調査や除去、封じ込め、囲い込みといった作業については、補助金制度を行なっている自治体もあります。
補助対象となるアスベスト(石綿)は、吹き付けアスベストまたはアスベスト含有吹き付けロックウールとなっていることがほとんどです。
対象者となるのは補助対象建築物の所有者です。
要件はアスベスト調査や除去に関して他の補助金を受けていないこと、固定資産税などの税金の滞納をしていないことなどとなっています。
アスベストに関する補助金について相談する
アスベスト調査のための補助金制度は全国にありますが、ここでは東京都での実例をいくつか紹介します。
| 港区アスベスト対策費助成 | 吹付け材等のアスベスト含有検査に要する費用の1/2相当額(上限10万円) |
| 新宿区吹付けアスベスト含有調査費助成金 | 含有調査費の10/10 ただし上限25万円/棟 |
| 民間建築物アスベスト対策費助成(台東区) | 調査に要した費用の1/2、かつ簡易調査10,000円、簡易調査以外の調査100,000円以内 |
| 江東区アスベスト分析調査助成 | 調査費用の1/2以内 限度額5万円 |
| アスベスト分析調査助成(品川区) | 含有分析調査費の10/10相当 上限5万円/棟 |
また、アスベスト除去工事にも補助金制度がある自治体もあるので、事前によく確認しておきましょう。
解体工事の補助金・助成金については、以下の記事を参考にしてください。

令和4年(2022年)4月以降、解体工事部分の床面積が80㎡以上、または請負金額が100万円以上の改修工事は、事前調査結果の労働基準監督署への電子届け出が必要になります。
また、令和5年(2023年)10月以降には事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う等の義務付けなど、今後も改正が進む予定となっています。

大気汚染防止法の一部を改正する法律が2020年6月5日に公布され、一部の規定を除いて2021年4月から解体工事を行う前にアスベスト調査を行うことが義務化されました。
これによって罰則が強化されると共に、都道府県等による立入検査の対象が拡大されて、有資格者による解体工事前のアスベスト調査も義務付けられます。(令和5年10月から施行)
解体工事前のアスベスト事前調査では、解体工事の施主(発注者)にも業者の事前調査が適切に行えるように情報を提供する義務が発生します。
そのため、何よりも法改正に対応できる業者選びをすることが今後ますます重要になっていくでしょう。
アスベスト調査や業者選びにお悩みの方は、解体エージェントにお気軽にご相談ください。
関連記事:
\ 見積もり後のお断りも大丈夫 /

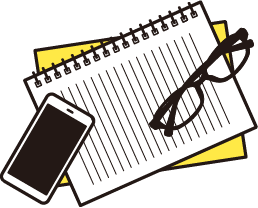
2022年04月05日
住宅の解体工事を行う際には、解体工事の前に浄化槽の汲み取りが必要です。 汲み取りを行わないまま解体工事をしてしまうと溜まった生活排水が地下に流れ出てしまい、地下水や土などに悪影響を与えてし...
2022年04月05日
建物の解体を検討しているのですが、建材にアスベストが含まれていた場合は解体費用が高額になると聞いたため、アスベスト含有の有無を自分で調べる方法が知りたいです。 アスベスト含有の有無は建物の築年...
2021年04月23日
家屋の解体工事は一般の方でも何となくイメージできると思いますが、駐車場の解体工事となるとイメージできる方が少ないのではないでしょうか。 駐車場にはアスファルトやコンクリートで舗装されただけの...